 好評
好評 〈事態把握〉における日韓話者の認知スタンス : 認知言語学の立場から見た補助動詞的な用法の「ていく/くる」と「e kata/ota」の主観性
徐珉廷 著
言語類型論的に似ていて、ともに主観的な把握を好むとされる日本語と韓国語に注目し、両言語の〈事態把握〉の異同について研究している。日本語の「ていく/くる」と韓国語の「e kata/ota」の補助動詞的な使い方についての分析を通して、両言語の主観性の度合いを明らかにする。
 好評
好評 徐珉廷 著
言語類型論的に似ていて、ともに主観的な把握を好むとされる日本語と韓国語に注目し、両言語の〈事態把握〉の異同について研究している。日本語の「ていく/くる」と韓国語の「e kata/ota」の補助動詞的な使い方についての分析を通して、両言語の主観性の度合いを明らかにする。
 日本語教育学の新潮流
日本語教育学の新潮流 向山陽子 著
Skehanの主張に基づき、言語分析能力、音韻的短期記憶、ワーキングメモリの3つの適性要素が、第二言語としての日本語学習に与える影響を縦断的に検討した結果をまとめた研究書。
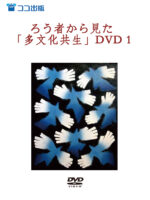 シリーズ 多文化・多言語主義の現在
シリーズ 多文化・多言語主義の現在 佐々木倫子・岡典栄 編
このDVDは、「手話」を切り口に、言語的・文化的マイノリティとしてのろう者の存在と、その課題を明らかにした書籍『ろう者から見た「多文化共生」』(ココ出版)の内容を、執筆者本人が日本手話で語りなおしたものです。
 言語教育実践 イマ×ココ
言語教育実践 イマ×ココ 実践持ち寄り会 編
『イマ×ココ』は、言語教育における実践の共有をめざす雑誌(年刊)です。現場の実践を丸ごと記し・伝えること、それを共有し、それぞれの眼差しで意味づけることで、実践をより豊かで多様なものに変えていくことができる、という信念の下に生まれた雑誌です。
 好評
好評 近藤彩 編著 金孝卿・池田玲子 著
日本語の習得そのものではなく、ビジネスの現場で起きる問題を解決し、課題を達成できる能力、そして、異なる考え方を持つ人とも人間関係を損ねることなく仕事を進めていける能力を育てることを目指した新しい日本語教材。
 日本語教育学研究
日本語教育学研究 細川英雄 著
「ことばの市民」とは何か? 日本語教育における「学習者主体」の提案者が、ことばと文化の統合をめざした実践研究を経て、第三の道程にいたる言語文化教育学の思想。言語教育の未来を照らす一条の光。15編の論考と5つの論点を収録。
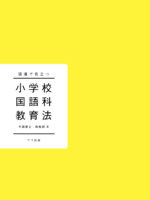 好評
好評 牛頭哲宏・森篤嗣 著
ベテラン教師と研究者が共同で執筆した国語科指導法のテキスト。現場教師のワザと研究者の理論を織り交ぜ、丁寧に、教育現場ですぐに役立つ指導法を解説。学習指導案の作成や模擬授業などを通して、発問や板書の技術も含めた実践的な指導方法を学べます。
 一橋日本語教育研究
一橋日本語教育研究 一橋日本語教育研究会 編
一橋日本語教育研究会の研究会誌。一橋日本語教育研究会とは、一橋大学大学院言語社会研究科第2部門に所属する現役学生、修了生および、教員を中心とした研究会で、2012年に設立された。年一回刊行。
 シリーズ 多文化・多言語主義の現在
シリーズ 多文化・多言語主義の現在 佐々木倫子 編
ろう者とは誰か? そして、何が彼/彼女たちを不可視の存在としてきたのか? 本書は、「手話」を切り口に、言語的・文化的マイノリティとしてのろう者の存在と、その課題を明らかにする。
 日本語/日本語教育研究
日本語/日本語教育研究 日本語/日本語教育研究会 編
2009年に設立された日本語/日本語教育研究会の研究会誌第3号。