 一橋日本語教育研究
一橋日本語教育研究 一橋日本語教育研究 2号
一橋日本語教育研究会 編
一橋日本語教育研究会の研究会誌。一橋日本語教育研究会とは、一橋大学大学院言語社会研究科第2部門に所属する現役学生、修了生および、教員を中心とした研究会で、2012年に設立された。年一回刊行。
 一橋日本語教育研究
一橋日本語教育研究 一橋日本語教育研究会 編
一橋日本語教育研究会の研究会誌。一橋日本語教育研究会とは、一橋大学大学院言語社会研究科第2部門に所属する現役学生、修了生および、教員を中心とした研究会で、2012年に設立された。年一回刊行。
 日本語教育学の新潮流
日本語教育学の新潮流 宇佐美洋 著
外国人の書いた「謝罪文」に対する日本人の「評価」を調査し、日本人が、外国人の日本語に対して、どのような印象を抱き、価値判断を行っているのか、そのプロセスをモデル化して提示する。
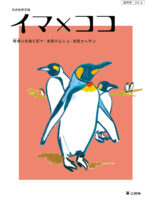 言語教育実践 イマ×ココ
言語教育実践 イマ×ココ イマ×ココ編集委員会 編
『イマ×ココ』は、言語教育における実践の共有をめざす雑誌(年刊)です。現場の実践を丸ごと記し・伝えること、それを共有し、それぞれの眼差しで意味づけることで、実践をより豊かで多様なものに変えていくことができる、という信念の下に創刊されました。
 好評
好評 庵功雄・イ ヨンスク・森篤嗣 編
「やさしい日本語」の持つ3つの側面(補償教育の対象/地域社会における共通言語/地域型初級の対象)を軸に議論を展開しつつ、「外国人」だけでなく、「視覚/聴覚障がい者」へも対象を広げ、その可能性をさぐる。
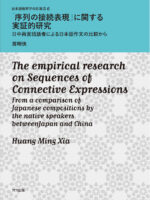 日本語教育学の新潮流
日本語教育学の新潮流 黄明侠 著
中国語を母語とする日本語学習者が書いた説明文と意見文に出現する序列の接続表現を分析し、その特徴と問題点を、日本語母語話者との比較の中で考察した一冊。
 日本語/日本語教育研究
日本語/日本語教育研究 日本語/日本語教育研究会 編
2009年に設立された日本語/日本語教育研究会の研究会誌第4号。
 日本語教育学の新潮流
日本語教育学の新潮流 尾関史 著
複数の言語や文化の中で育つ子どもたちは、複数のことばをどのように捉え、どのように学ぶのか。そして、その過程でどのようなアイデンティティを形成しながら成長していくのか。本書ではこれらの問いに答えつつ、複数言語環境を生きる子どもたちへの「ことばの教育」を再考する。
 日本語教育学の新潮流
日本語教育学の新潮流 向山陽子 著
Skehanの主張に基づき、言語分析能力、音韻的短期記憶、ワーキングメモリの3つの適性要素が、第二言語としての日本語学習に与える影響を縦断的に検討した結果をまとめた研究書。
 言語教育実践 イマ×ココ
言語教育実践 イマ×ココ 実践持ち寄り会 編
『イマ×ココ』は、言語教育における実践の共有をめざす雑誌(年刊)です。現場の実践を丸ごと記し・伝えること、それを共有し、それぞれの眼差しで意味づけることで、実践をより豊かで多様なものに変えていくことができる、という信念の下に生まれた雑誌です。
 日本語教育学研究
日本語教育学研究 細川英雄 著
「ことばの市民」とは何か? 日本語教育における「学習者主体」の提案者が、ことばと文化の統合をめざした実践研究を経て、第三の道程にいたる言語文化教育学の思想。言語教育の未来を照らす一条の光。15編の論考と5つの論点を収録。