 一橋日本語教育研究
一橋日本語教育研究 一橋日本語教育研究 1号
一橋日本語教育研究会 編
一橋日本語教育研究会の研究会誌。一橋日本語教育研究会とは、一橋大学大学院言語社会研究科第2部門に所属する現役学生、修了生および、教員を中心とした研究会で、2012年に設立された。年一回刊行。
 一橋日本語教育研究
一橋日本語教育研究 一橋日本語教育研究会 編
一橋日本語教育研究会の研究会誌。一橋日本語教育研究会とは、一橋大学大学院言語社会研究科第2部門に所属する現役学生、修了生および、教員を中心とした研究会で、2012年に設立された。年一回刊行。
 日本語/日本語教育研究
日本語/日本語教育研究 日本語/日本語教育研究会 編
2009年に設立された日本語/日本語教育研究会の研究会誌第3号。
 日本語教育学の新潮流
日本語教育学の新潮流 萩原孝恵 著
「だから」について、その機能体系と運用ルールを詳らかにした良書。テクストの論理性を導くとされてきた「接続詞」が、実際の使用に際しては「人間関係」という指標が軸になっていることが明らかになる。
 好評
好評 野呂博子・平田オリザ・川口義一・橋本慎吾 編
日本語教育史上初となる「演劇」を活用した教室活動のリソースブック。さらに、劇作家平田オリザ監修の書き下ろしシナリオを活用ガイドとともに収録。日本語学習者の口語コミュニケーション能力を高めたい日本語教師は必読です。
 好評
好評 今井新悟編著 赤木彌生・中園博美著
インターネット上で日本語学習者が日本語能力を測ることのできるテストJ-CATの公式ガイドブック。
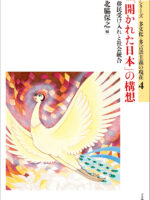 シリーズ 多文化・多言語主義の現在
シリーズ 多文化・多言語主義の現在 北脇保之 編
同化主義の陥穽に陥ることなく社会統合を行うことは可能なのか? 地方自治・経済・法律・教育・日本語教育・労働・福祉・地域の現場で、「多文化共生」の旗印の下に行われてきた、さまざまな実践を踏まえ、「開かれた日本」の在り方を模索する。巻頭に、中川正春氏を交えた座談会を収録。
 日本語/日本語教育研究
日本語/日本語教育研究 日本語/日本語教育研究会 編
2009年に設立された日本語/日本語教育研究会の研究会誌第2号。
 日本語教育学の新潮流
日本語教育学の新潮流 嘉数勝美 著
多言語・多文化化する日本社会の中で、日本語教育政策は、どのような思想・哲学に基づき、何を志向していくべきなのか。「グローバリゼーション」、「ユニバーサリティ」「アイデンティティ」「公共性」などをキーワードに、その答えを提示する。
 好評
好評 日本語教育政策マスタープラン研究会 著
日本で生活する外国人や日本語を母語としない人たちが、日本社会の一員として社会参加するためには、日本語教育が必要である。すべての人が「自己実現」できる、本当の「多文化共生社会」をつくるために、「日本語教育にできること」を提案する。
 日本語教育学研究
日本語教育学研究 トムソン木下千尋・牧野成一 編
外国語教育の新しい潮流である「内容重視の言語教育(CBI: Content-based instruction)」の日本語教育における可能性と課題を明らかした論文集。